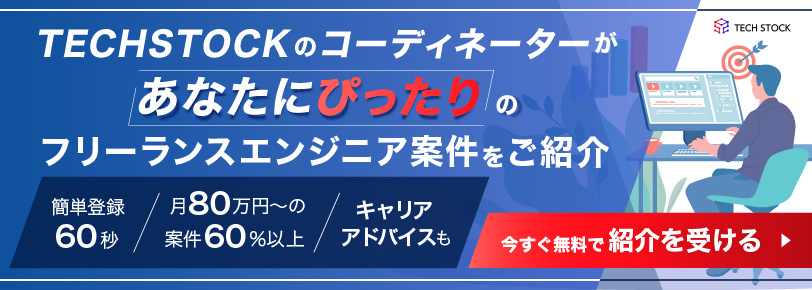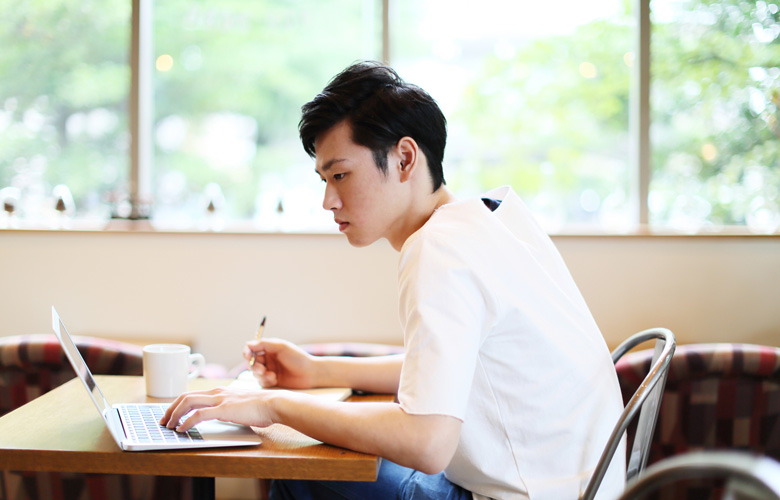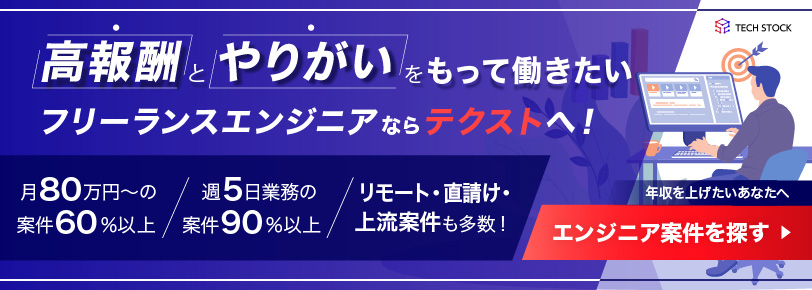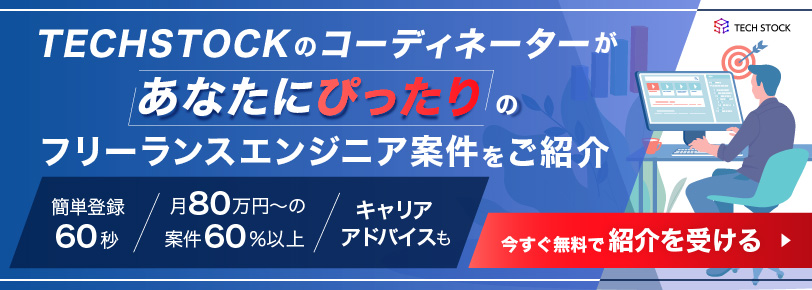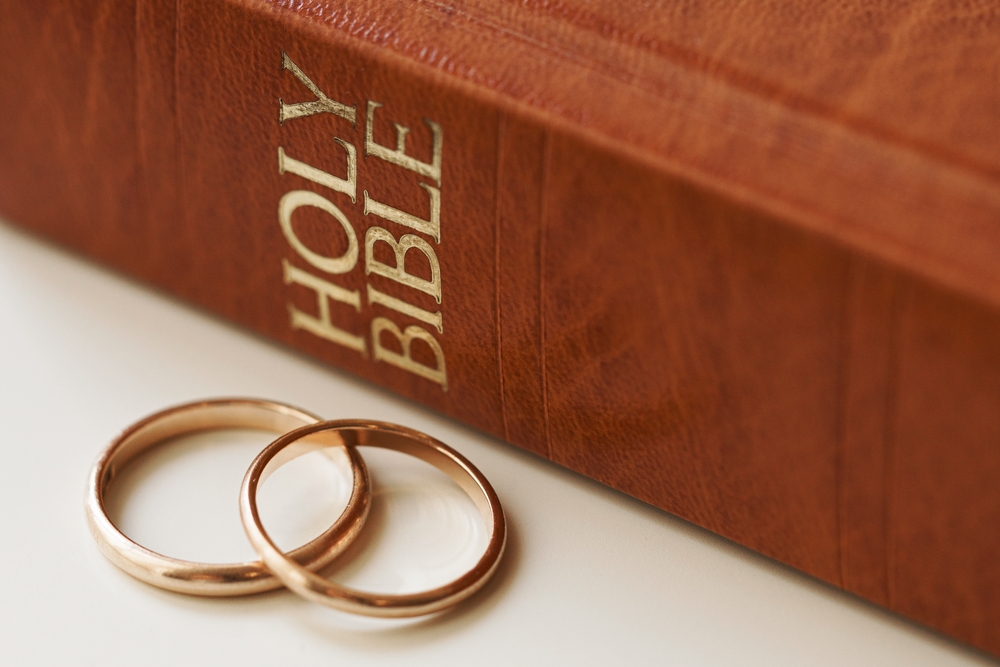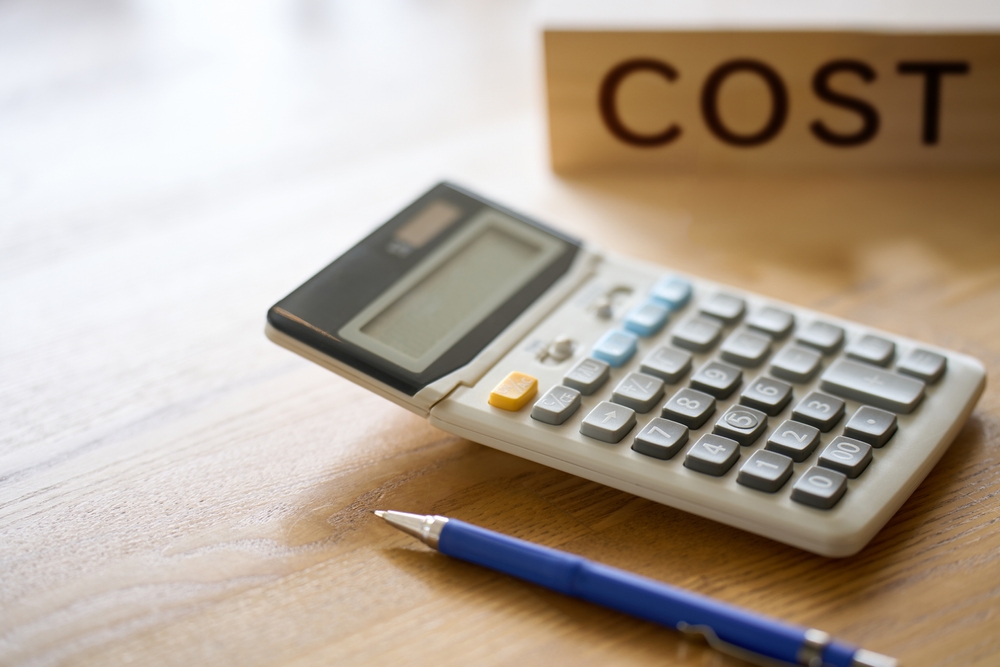未経験からシステムエンジニアになるには?SEの仕事内容・必要なスキル・学習方法を解説
就職して現在の仕事に慣れてきたが、ふと「このままの仕事でいいのだろうか」と不安になることは、誰しも一度はあるのではないでしょうか。その将来性への不安を払拭するためにも、他の職種について調査してみるのは有意義なことです。
この記事ではシステムエンジニアの仕事内容や年収とともに、システムエンジニアになるにはどのようなことが必要かをご紹介します。

システムエンジニア(SE)とは
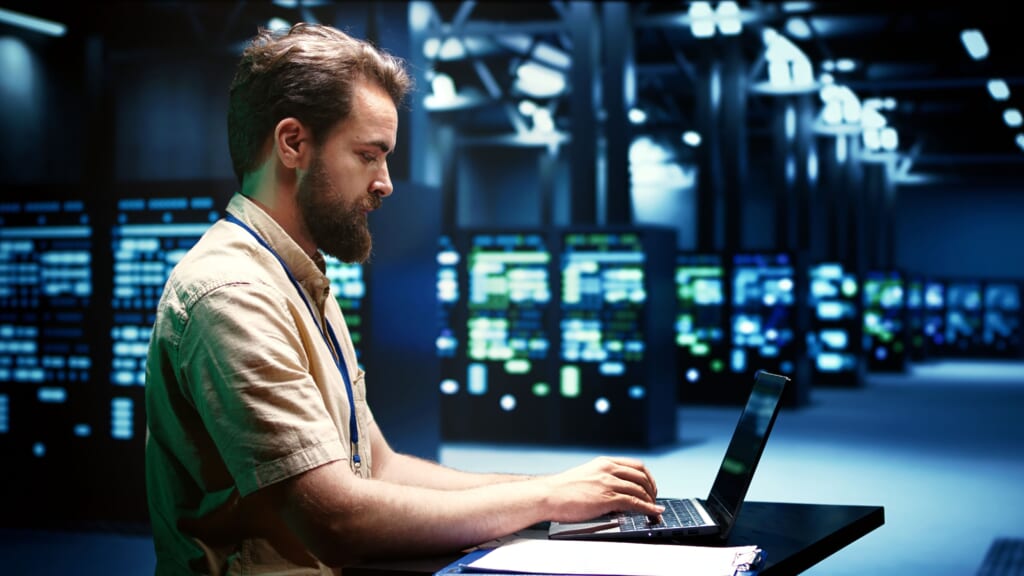
システムエンジニア(SE)は、顧客の情報システムの開発やWebサイトの開発を受託し、それらの設計・開発を行う職種です。金融や製造など、システムエンジニアが関わる業界は多岐にわたります。また業務システム開発、Webサイト開発のほかにも、機器にプログラムを施す組み込みエンジニアや企業の情報システム部門を司る社内SEがあります。
システムエンジニアの年収
システムエンジニア(SE)の年収はスキルや企業規模によって大きく異なります。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」(2019年度)によると、SEの平均年収は約568万9000円です。
システムエンジニアの年収についてくわしく知りたい方は、下記の関連記事をご参照ください。
システムエンジニアの働き方
これからシステムエンジニアになろうと考えている方の中には、どの企業に属しても同じと考える方もいるかもしれません。しかし、所属する企業のビジネスモデルによって、働き方は異なります。
ここでは、システムエンジニアが所属する代表的な事業形態3つを紹介します。これを参考に、どの形態に所属するか検討してみてください。
自社開発
自社開発はその名の通り、自社製品を開発し、その製品をエンドユーザーに販売する形態です。自社で開発をしているため、上流から下流まで一貫して経験できる機会が多く、納期に追われることも少ない傾向があります。
ただ、自社サービスの開発に用いられるプログラミング言語のみを使用する場合が多いため、さまざまなプログラミング言語を学びたい人には、向かない可能性があります。
SIer
SIerとは、他社の製品やサービスを代わりに開発し、利益を得るビジネスモデルです。さまざまな業界と取引をするため、幅広い知識や経験を身に付けられることがメリットです。
デメリットを上げるとすれば、自社開発に比べて納期が厳しく、繁忙期には忙しくなる可能性があります。
SES
SESは、エンジニアを他社へ派遣し、開発の手助けを行い、依頼料を受け取るビジネスモデルです。3つの業務形態の中で、未経験から挑戦しやすく、多種多様な経験・知識を得ることができます。
ただ、身に付けられるスキルが派遣先の企業に依存したり、一人で未経験の案件に入るとスキルを習得しづらかったりなどのデメリットも存在します。
システムエンジニア「きつい」「やめとけ」は過去の話?
システムエンジニアが「きつい」「やめとけ」といわれる理由
システムエンジニア(SE)について「きつい」「やめとけ」と言われたことはありませんか?その理由の大半は、長時間労働や納期のプレッシャーにあります。SEの仕事はシステム開発の進捗に大きく左右され、一つの工程の遅れがプロジェクト全体に影響を及ぼします。
そのため、納期前には残業や休日出勤が発生しやすいのが現実です。特に、大規模なシステム開発や、顧客の要望が頻繁に変わるプロジェクトでは、トラブル対応に追われることもあります。
また、システムトラブルや障害対応は、夜間や休日でも対応が必要になるケースがあり、心理的な負担も大きい職種です。こうした要因から、「SEはきつい」と言われることが多くなっています。
リモートワーク普及で働き方は改善傾向に
「きつい」「やめとけ」と言われることもあるシステムエンジニアですが、近年は働き方が大きく変化しています。リモートワーク普及やクラウド環境の整備、コミュニケーションツールの発展により、オフィスに出社しなくても開発業務が進められるようになりました。
柔軟な働き方が可能になったことで、ワークライフバランスを改善できるSEが増えているのです。
アジャイル開発やDevOps導入も労働環境改善に
アジャイル開発やDevOpsの導入により、従来のウォーターフォール型のプロジェクトと比べて短期間で区切った開発が進められるようになり、負担の分散も進んでいます。適切な環境を選べば、SEとして快適に働けるようになるでしょう。
システムエンジニアの基本的な仕事内容

システムエンジニアの基本的な仕事内容を、プロジェクトの流れとともに紹介します。
要件定義
クライアントから要望をヒアリングし、業務システムやWebサイトについて検討、どのようなシステムを開発するかを決めていくフェーズが要件定義です。クライアントとともに検討を重ね、クライアントが気づいていない業務上の課題を特定します。
このフェーズで主に議題となるのは、システムの概要や業務フロー、新システムの機能・性能や情報セキュリティ対策、スケジュールなどです。要件定義の段階で解決方法が曖昧な課題が残っていると後の工程に影響を与え、クライアントの要望に応えたシステムができないため、この時点で課題の対応可否についてよく検討しなければなりません。
挙げられた課題やシステムの形に対して協議した結果は、要件定義書というドキュメントにまとめ、次の基本設計」フェーズへ移ります。
基本設計(システム設計、外部設計)
基本設計(システム設計、外部設計)のフェーズでは、要件定義書をもとに、システムの構成や製作する機能や画面、帳票などを決めていきます。加えて、外部システムとの連携やデータベースの設計も行います。要件定義と同様、基本設計の段階で対応可否やその具体的な方法を定めておかなければなりません。
基本設計が定まらないまま詳細設計、プログラミング(開発)まで進んでしまうと、仕様ミスが発生した際に、改修の手戻りが大きくなる可能性があるのです。また改修の規模とシステム開発の受注価格が見合わなくなる恐れも考えられます。したがってこのフェーズで、綿密な設計が必要です。
基本設計の結果は基本設計書にまとめ、クライアントが確認、クライアントの合意があれば、次の「詳細設計」へ進みます。なお規模の小さなプロジェクトや改修では、基本設計と詳細設計をまとめて行うケースもあります。
詳細設計
詳細設計のフェーズでは、基本設計書をもとに機能を詳細に検討します。ここで検討するのはシステムで扱うデータ形式やファイル形式、内部処理の方法や流れなどです。業務システムの画面や、Webデザイナーが作成した画面デザインもチェックします。
設計の結果は、詳細設計書にまとめます。詳細設計書は、画面構成やデータベース、プログラム内容、データ形式、各種制約、画面遷移や処理などが図解も含めて説明がされたものです。これらのドキュメントをベースに、プログラマーが実際に開発を行うことになります。
プログラミング(開発)
詳細設計書をもとに、プログラマーにより実装を行うフェーズです。システムエンジニアはプログラマーたちの進捗確認や仕様変更の連絡など、開発の取りまとめとしての役割を担います。実装後のプログラムごとのテスト(単体テスト)は、後工程のテストではなくプログラミング(開発)フェーズに含まれることもあります。
プログラミングフェーズの主体となるのはプログラマーです。プロジェクトや組織の体制によって、システムエンジニアは詳細設計までを担当し、実装を外部人材に依頼するケースがあります。また小規模のプロジェクトの場合には、システムエンジニアがプログラマーを兼務して、プログラミングを行うこともあります。
テスト
テストフェーズでは、「結合テスト」や「総合テスト」が行われます。「結合テスト」は、ある単位のプログラム群で複数のプログラムや外部システムとの連携をテストするものです。一方の「総合テスト」は、すべての要素に対して確認を行い、動きを確かめるテストです。
さらにWebサイト開発の場合には開発方針によって、一般のモニターによって動作を確認する「ユーザビリティテスト」が行われます。
テストが進むと関係人数が増えていき、総合テストの段階では品質管理部門や情報セキュリティの担当者も参加することがあります。システムエンジニアはテストで不具合が発生すれば、開発チームと共同で修正しなければなりません。テストフェーズが終われば、いよいよ情報システムやWebサイトはクライアントに納品できる状態となります。
検収・導入
検収・導入のフェーズでは、クライアントの受入テスト(検収)を行います。クライアントとともに、システムが設計通りに動くかどうかや、品質に問題がないかをチェックし、万が一不具合があれば、システムエンジニアやプログラマーが修正することになります。
受入テストが無事終了すれば、いよいよシステムの導入です。クライアント企業の影響度を考え、導入スケジュールを組みます。また導入の前後で、システムを利用する社員・関係者、Webサイトの運用者に対して、操作や運用に関する教育を行います。
運用・保守
導入後は運用・保守のフェーズです。システムの運用開始後は不具合がないように監視し、不具合があれば対応します。システムが順調に稼働するまで、システムエンジニアがクライアント企業へ常駐することもあります。
日々の運用では、システムの起動/停止やバックアップ、クライアントからの問い合わせ対応などが主な業務です。保守業務では、システムの挙動が通常と異なる場合の対応を行います。運用チームは新たな要望が出た際の窓口となることもあります。
システムエンジニアと他の職種の違い

IT系の職種には、システムエンジニアと混同されやすい職種があります。例として、プログラマーとプロジェクトマネージャーについて、違いを簡単に見ておきましょう。
システムエンジニアとプログラマーの違い
プログラマーは一般的に、システムエンジニアが作成した詳細設計書をベースにプログラミングする職種です。プログラムが出来上がったら単体テスト(動作確認)を実施し、不具合が見つかった場合は修正を行います。プロジェクト方針によっては、結合テストや総合テストもシステムエンジニアとともに実施することもあります。
プログラマーは、いわばシステムエンジニアの前段階の職種です。
システムエンジニアとプロジェクトマネージャーの違い
プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの責任者です。開発計画に基づいてプロジェクト実行計画を作成し、人員・リソースの調達や予算管理を行います。またクライアントにプロジェクトの進捗や課題、対策を報告し、必要となれば追加予算について検討を促すなど、プロジェクトが滞りなく進むよう努めます。
プロジェクトマネージャーは、システムエンジニアのキャリアパスのひとつです。
働き方改革(※)に合わせて、フリーランスとしての働き方が注目を集めています。
しかし、フリーランスに興味はあるものの、どのような職種が適しているか、会社員と働き方がどのように異なるかわからない人も多いのではないでしょうか。
本記事では、フリーランスとしての基礎知識やおすすめの職種などを解説します。
フリーランスとして働き始めるための準備や手続きなどもステップバイステップで解説しますので、ぜひ参考にしてください。
※参考:「働き方改革」の実現に向けて|厚生労働省
システムエンジニアになるには

未経験の状態でシステムエンジニアになるのは簡単ではなく、ある程度知識とスキルを備えることが必要です。システムエンジニアになるための進路を挙げます。
大学・専門学校で学ぶ
大学の情報系学部へ進学するのが選択肢のひとつです。プログラミングやWebマーケティングなどITに関する知識だけでなく、経済学や心理学などの一般教養も学べます。大学卒業者以上を雇用している企業もあり、就職の際にも幅広い就職先を検討することが可能です。
またITの専門学校でも専門知識が学べます。学校によっては夜間コースを設置していたり、独自の就職支援を行っていたりと、専門知識を得るだけではないサポートをしている学校もあります。
プログラミングスクールへ通う
初心者からでもプログラミングを専門的に学べるのがプログラミングスクール。オンラインで開講しているスクールもあります。システムエンジニアの中途採用開発経験が求められるケースが多いのですが、プログラミングスクールの中には未経験者に開発経験を積ませた上で、就職先や業務委託案件を紹介するサービスを提供しているケースも多いです。
TechAcademy(テックアカデミー)
現役エンジニアが講師を務めるオンラインプログラミングスクールです。JavaやPythonを使用したWeb制作やAI・データ分析等さまざまな講座があります。
参考:テックアカデミー
COACHTECH(コーチテック)
実際のWebアプリ案件を受注でき、経験も積めるオンラインスクールです。Webアプリケーションコースがあり、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月の4つのプランから選ぶことができます。
参考:COACHTECH
DMM WEBCAMP
プログラミングやWebデザインが学べるオンラインスクールです。「はじめてのプログラミング」やPHP、Javaなどの各プログラミング言語の講座が用意されています。
参考:DMM WEBCAMP
独学
システムエンジニアとしての技術は独学でも習得可能です。オンライン講座や書籍などで学習した後に、自分で小さなシステムを製作することで、要件定義から各種設計、開発、テストまで一通りの業務を経験できます。
ただ独学の場合は、実務経験を積むことが難しいケースもあります。少なくともプログラマーとして最低限のスキルを習得し、クラウドソーシングなどに経験の場を求めるのもひとつの手です。
Progate
Progateは、初心者向けにスライド形式で学習を進められるプログラミング学習サイトです。環境構築なしで学習でき、PythonやJava、SQLなどSEに必要な基礎技術を習得できます。ハンズオン形式で基礎を固め、初めてプログラミングに触れる人に最適。SEを目指すなら、入門編を終えた後に実践的な開発へ進むと効果的です。
Udemy
Udemyは、プロのエンジニアや講師が提供する動画講座を購入し、好きなペースで学習できるプラットフォームです。システム設計やクラウド、DevOpsなど、実務に役立つスキルを深く学べます。SEとして求められるスキルを網羅できるため、独学でも現場レベルの知識を得るのに有用。定期的なセールで安価に学べる点も魅力です。
ドットインストール
ドットインストールは、3分動画で手軽に学べる日本語のプログラミング学習サイトです。HTML/CSS、JavaScript、PHPなどWeb系技術が充実しており、フロントエンドやサーバーサイドの基礎を学ぶのに適しています。短時間で基礎を習得し、システム開発の入門として活用可能です。コードを書きながら実践的に学べる点も魅力です。
フリーランスエンジニアの案件紹介サービスTECH STOCKでは、身に付けている現状のスキルと今後習得すべきスキルを目指したいキャリアに照らし合わせて、最適なキャリアカウンセリングを行います。キャリアのご相談もTECH STOCKにお任せください。
TECH STOCKはフリーランス・ITエンジニアのための案件紹介サイトです
システムエンジニアに必要なスキル

未経験からシステムエンジニアに挑戦するにあたり、最低限必要なスキルを挙げます。
開発スキル
プログラミングスキル
システムエンジニアがプログラミングを行うとは限りませんが、プログラミング知識は必須です。システムエンジニアの業務は、クライアントからの要望をシステムとして設計することがメインですが、実現可能かどうかを判断するためには使用するプログラミング言語に精通しておかなければなりません。
使用するプログラミング言語はプロジェクトによって異なります。現在よく使われているプログラミング言語はPython、C++、C言語、Javaなどです。複数の言語やフレームワークの知識もある程度あると、設計業務も進めやすくなります。
設計スキル
クライアントの要望を情報システムに落とし込む設計スキルも必要です。情報システムを設計するにはプログラミングだけでなく、ハードウェアやネットワーク、周辺機器、クラウドなど幅広い知識が必要となります。周辺で使われている技術と情報システムが、スムーズに連携ができるようにしなければなりません。
マネジメント能力
マネジメント能力も、システムエンジニアが身につけていくべき能力です。システムエンジニアはプロジェクトマネージャーほどのマネジメント業務をするわけではありませんが、プログラマーを含む開発チームのリーダーを兼ねることがあります。その場合にはチームメンバーの進捗や負荷状況を把握し、ときにはメンバーの追加をプロジェクトマネージャーに申し出るなど、開発チーム全体が滞りなく進めるためのスキルが必要です。
また、システムエンジニアの経験年数が重なっていくと、プロジェクトマネージャーの下について予算や工程を管理することもあります。
コミュニケーション能力
開発には、コミュニケーションが重要です。システムエンジニアはクライアントからのヒアリング、開発チームとの調整などで、社内外でコミュニケーションを取ることになります。
クライアントからは要望や問題点の聞き出し、解決策の提案や追加要望の取りまとめを行い、開発チームのメンバーとは進捗を注視しつつ、円滑にチームを回さなければなりません。このようにシステムエンジニアはIT技術のみならず、人間関係を構築するスキルも必要となるのです。
問題解決能力
クライアントの課題に対して、情報システムによって問題解決する能力は、システムエンジニアに欠かせません。問題を解決するためには、まず正確な情報をヒアリングし、本質を見極めることから始まります。
次に分析のための考え方を活用し、仮説を立てて実現可能性を追求したり、論理的思考力を用いて解決策を検討したりします。この検討の繰り返しで問題を解決していくことになるのです。
SE業界は「AI」「リモートワーク」でどうなる?動向を予測

未経験からシステムエンジニアへの転身を考えているなら、今後の業界の動向は気になるのでは。
「AI」「リモートワーク」などのキーワードから考えられる、今後のシステムエンジニアの動向を予測します。
AIがSE業界に及ぼす影響は?
発展著しい生成AIによってコードの自動生成やデバッグ支援が可能となり、開発効率は日夜向上しています。システムエンジニア(SE)は単純なコーディングからは解放され、思考・発想が求められる業務に集中できるようになっています。
AI活用でコーディング作業の一部が自動化されることで、エントリーレベルのポジションが減少する可能性も指摘されているものの、AIを使いこなして価値を創出できるSEについては引き続き高い需要があると考えられています。
AI(人工知能)は近年急激に生活に普及し、私たちの生活に変革をもたらしました。特にChatGPTやGemini、Microsoft Copilotなどの生成AIは、日常生活だけでなくビジネスの場でも広く利用されています。これらのAIの普及によって、今後なくなる職種があることが指摘されています。しかし一方で、AIが新しく作業をすることで新しく生まれる仕事があります。本記事では、アメリカのITサービス大手のコグニザントという会社が出版した「What to do when machines do everything」という本で紹介されていたAIによって「新たに生まれる仕事」をご紹介します。
また、淘汰されずに残る仕事とこれからのAI時代をどう生き抜くべきかについてもご紹介します。
TECH STOCKでは、今後AIが社会に与える影響や求められるスキルについて解説する資料を配布しています。今後のAIの発達や社会の変化に関心がある方はぜひご覧ください。
リモートワーク普及でSEの労働環境は変わる?
リモートワークは政府が推進する働き方改革の一環として、今後も普及が進むと予想されています。リモートワークのデメリットも指摘されているためフルリモート案件は減少傾向にあるものの、リモートと出社を併用する「ハイブリッドワーク」は増加しています。高度なコミュニケーションツールやコラボレーションツールの開発により、リモートワークでもオフィス勤務と遜色ないチームワークが実現されるでしょう。
システムエンジニアに向いている人の特徴

システムエンジニアに向いている人の特徴をシステムエンジニアのやりがいとともに紹介します。
論理的思考ができる人
複雑な問題を論理的に分析して最適な解決策を提案できる人は、システムエンジニアに向いています。クライアントが抱える課題を正しく把握して分析し、解決まで導くことがシステムエンジニアとして市場価値を高める近道なのです。
学習意欲・探究心・向上心の高い人
IT業界は移り変わりが早く、最新の技術や知識の習得が求められます。したがって、システムエンジニアには年齢や経験に関係なく常に学び続ける姿勢が不可欠です。プログラミングだけでなく、データベースやネットワークやクラウド、生成AIなど幅広く知識を習得し続けるのは大変ですが、成長につながります。自主的に学習し、成長することにやりがいを感じられる人はシステムエンジニアに向いていると言えます。
根気強い人・我慢強い人
プログラミング(開発)や検収、システム導入後などでは、ときに不具合の修正に長く取り組まなければならないケースがあります。システムエンジニアには、苦しい状況でも最後までやり遂げられる根気強さが求められます。また、環境の変化や忙しさに耐えられる人もシステムエンジニアに向いています。
システムエンジニアの資格

学習方法の一つとして、資格取得を目標に勉強するという方法があります。資格取得を目標にすると体系立てて理解でき、ある程度新しい知識も得ることが可能です。また企業の採用面接者などへ、資格があることをアピールすれば、知識やスキルを有していることを客観的に証明できます。
ただし、システムエンジニアの資格は「取得すればシステムエンジニアになれる」という類の資格ではないため、あくまで「自分の能力の証明」と考えておきましょう。
ITパスポート
ITを利活用しているすべての社会人や、今後社会人となる学生が身につけておくべきITの基本知識を有していることを証明する国家資格です。
問われる内容はAI、IoTなどの新しい技術、アジャイルなどの新しい手法の概要、経営戦略やマーケティングなどの経営全般、セキュリティやネットワークなどのIT知識、プロジェクトマネジメントの知識など幅広い分野が網羅されています。
| 実施方式 | CBT方式(Computer Based Testing方式:パソコンを使用して解答) |
| 実施時期 | 随時実施 |
| 試験時間 | 120分 |
| 出題数 | 100問 |
| 試験費用 | 7,500円(税込) |
| 合格率 | 51.1% ※平成23年度~令和4年度の平均 |
公式サイト:ITパスポート試験
基本情報技術者
ITを活用したシステムやソフトウェアを作る人材に向けて、基本的な知識や技能、活用能力を有していることを証明する資格です。
上位者の指導のもと、IT戦略に関わったり、システム・サービスの提案活動に参加したり、ソフトウェアを設計したりできる能力のほか、プログラムを作成できることも求められます。
| 実施方式 | CBT方式(Computer Based Testing方式:パソコンを使用して解答) |
| 実施時期 | 随時実施(※令和4年度までは年2回実施) |
| 試験時間 | 科目A:90分 科目B:100分 |
| 出題数 | 科目A・出題数 60問 解答数 60問 科目B・出題数 20問 解答数 20問 |
| 試験費用 | 7,500円(税込) |
| 合格率 | 41.2% ※令和6年度の合格率 |
応用情報技術者
基本情報技術者よりも高度な資格で、応用的知識や技術を身につけていることを証明します。
経営戦略やIT戦略の策定においては、経営者の方針や経営を取り巻く外部環境を理解し、情報収集や分析を行えることが求められます。また要件定義やシステム設計など各開発フェーズにおいても、調査・検討が自ら行えるだけのスキルも必要です。プロジェクトマネージャーの下で、予算や品質、工程を管理できることも求められます。
| 実施方式 | 筆記 |
| 実施時期 | 年2回 春期(4月)、秋期(10月) |
| 試験時間 | 午前:150分 午後:150分 |
| 出題数 | 午前・出題数 80問 解答数 80問 午後・出題数 11問 解答数 5問 |
| 試験費用 | 7,500円(税込) |
| 合格率 | 29.2% ※令和7年度春期 |
まとめ
「システムエンジニアになるにはどうすればよいか」を中心に、必要なスキルや挑戦しやすい難易度の資格をご紹介しました。システムエンジニアはキャリア前段階のプログラマーから始まり、システムエンジニアの経験を積んだ後はプロジェクトマネージャーやその他専門分野を極める職種など、キャリアパスが多彩です。
現在、システムエンジニアに転身しようか迷っている人は、今自分ができることとこれから身につけるべき技術を洗い出し、ぜひ挑戦してみてください。