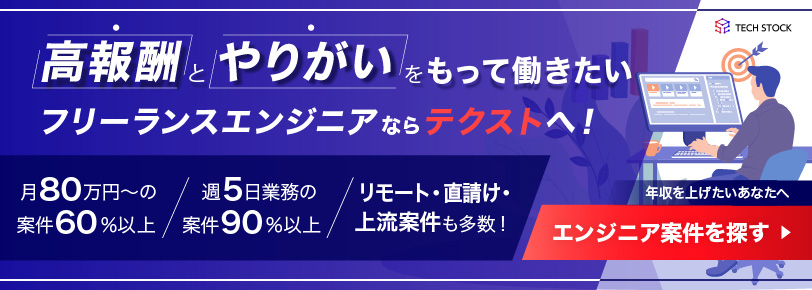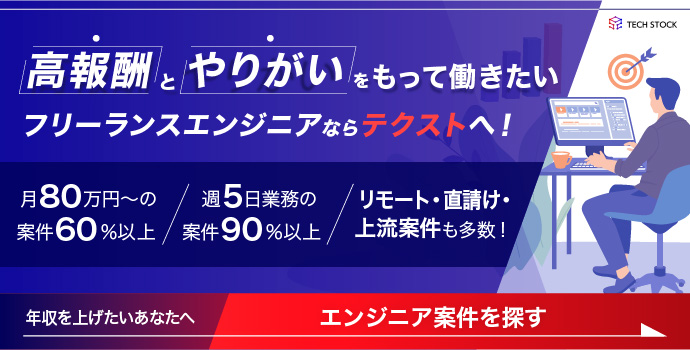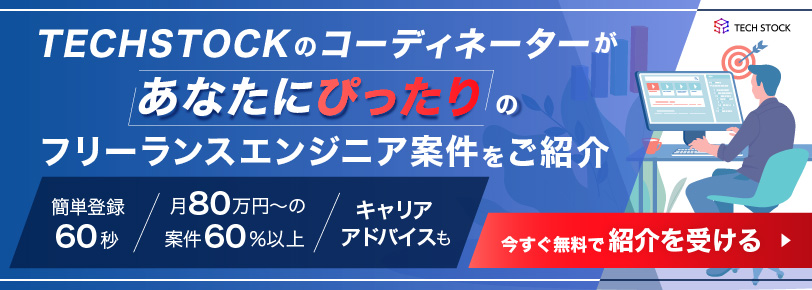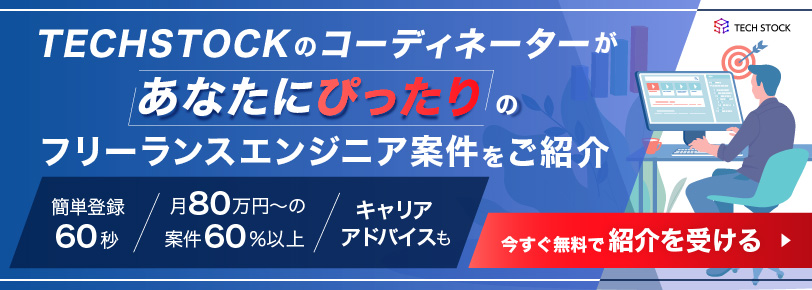SIとは?SIerとの違いや具体的な案件例、現状と将来性まで解説
IT社会の現代でよく耳にする「SI」はシステムインテグレーションの略称で、クライアントが利用するシステムの要件定義から開発、導入後の運用・保守まで一貫して行うサービスのことです。
本記事ではSIやSIerの意味を解説し、SI案件について詳しく紹介します。SI案件の現状・将来性やメリット・デメリットも紹介するので、SI案件に興味がある方はぜひお役立てください。

SIとは?意味や類義語との違いを解説

IT業界ではよく目にする「SI」という言葉は、何を意味しているのでしょうか。
まずは、SIとはどのような意味なのか解説します。また、SIと混同されやすい言葉「SE」との違いについても説明します。
SIとは「システムインテグレーション」の略称
SIとはシステムインテグレーション(System Integration)の略です。Integrationは「統合」という意味を持っていることから、SIとは顧客が求めているシステムについて要件定義から運用・保守まで一貫して手掛けることを指します。具体的には、以下のような業務を請け負います。
- 要件定義
- 基本設計
- 詳細設計
- 開発
- テスト
- 導入
- 運用・保守
SI案件では、上記すべての工程を手掛ける場合だけではなく、部分的に介入する場合もあります。また、システム(ソフトウェア)のほか、コンピューターや周辺機器などのハードウェアの選定・導入や、ネットワーク回線の構築などもサポートします。
フリーランスエンジニアの案件紹介サービスTECH STOCKには、SI案件が多数ございます。高単価・上場企業・即アサイン可能など、スキルや希望にマッチする案件をご紹介します。フリーランスになって年収アップを狙うならTECH STOCKにお任せください。
TECH STOCKはフリーランス・ITエンジニアのための案件紹介サイトです
SIerとは「システムインテグレーター」の略称
SIから派生した言葉として「SIer」があります。SIerはシステムインテグレーターの略称で「エスアイヤー」と読みます。
SIに「~する人」を意味する「er」がついた言葉なので、SIを行う人を意味しています。SIを行う企業のことをSIerと呼称する場合もあります。ただし、SIerは和製英語のため英語圏では通じません。英語圏ではSIerではなく「System Integrator」と言います。
SIとSEの違い
SIとSEは、文字が似ていることから混同されることがあります。ただし、両者は別のことを指しているため、区別して使用しましょう。
SIとは、先述の通り、システムの開発や運用などを一貫して手掛けることです。一方のSEとは、システムエンジニアの略称で、システムを設計したり開発したりする人を指しています。つまりSI案件にはSEの技術力が必要で、SIとSEは密に関わり合う関係です。
SIerの分類

日本において、SIerの企業は大まかに以下の3つに分類できます。
- メーカー系SIer
- ユーザー系SIer
- 独立系SIer
それぞれの特徴を解説します。
メーカー系SIer
ハードウェアの開発を中心に、ソフトウェアやシステムの開発まで幅広く行っているのがメーカー系SIerです。
大手メーカーには多くの関連企業があり、コンピューターやサーバー製品など多様なハードウェアを製造しています。そのため、メーカー系SIerは自社グループ内のハードウェアを組み合わせて提案できる点が強みです。
ユーザー系SIer
ユーザー系SIerとは、自社で大規模なシステム開発を始めたことを契機として、システム開発部門を独立させてSIerとなった企業です。主に、金融業界、製造業界、通信業界、商社などから派生したユーザー系SIerが多く存在します。
ユーザー系SIerは、母体となっている親会社のSI案件を中心に、他社のSI案件も幅広く手掛けます。
独立系SIer
独立系SIerは、もとからSI案件専門で設立された企業です。
特定の親会社や関連企業を持たないため、提案内容に制限がありません。そのため、さまざまなメーカーのハードウェアを組み合わせたり、最新の技術を柔軟に取り入れたりするなど、顧客に最適な提案ができる点が特徴です。
SI案件の流れ

SI案件は、要件定義から設計、開発、運用まで一貫して手掛けます。そのため、以下のようにプロジェクトを工程別に細分化して、順を追って進めていく方法が一般的です。
- システムの要件定義を行う
- システムを設計する
- システムを開発する
- 完成したシステムをテストする
- 納品後、運用・保守を行う
それでは、それぞれの工程について詳しく解説します。
システムの要件定義を行う
まず、顧客からの依頼を受けて、SIer側が顧客が求めている要求をまとめ、システムに必要な機能や性能などを定義します。システム化の対象業務を洗い出し、業務処理の手順やシステムの操作、入出力要件などを整理して要件定義書としてまとめます。
ウォーターフォール型の開発では後戻りすることが難しいため、非常に重要なフェーズであり、また顧客との認識のズレをなくすという意味でも要件定義書にまとめる作業は大切な業務です。経験豊富なSEやコンサルタントが主に担当します。
システムを設計する
次は、要件定義書を基にして、具体的なシステムの仕様を設計書に記載していきます。
設計書がないままシステム開発を進めてしまうと、途中で変更や修正が入ることがあり、納期や予算がオーバーする場合があります。そのため、開発前に設計書にて具体的な仕様を定めておくことで、後からの修正・変更がないよう調整できます。
設計業務は、基本設計(外部設計)と詳細設計(内部設計)の2つに分けられます。
基本設計(外部設計)では、画面などの実際に利用する側が目にするユーザーインターフェースを設計します。ユーザーにとって使いやすいシステムを開発するための重要な工程です。
詳細設計(内部設計)では、基本設計の内容をもとに開発するシステムを大まかな機能ごとに分割し、それら機能の間をつなぐインターフェースの仕様などを設計します。基本設計とは逆に、詳細設計においてはプログラム設計など、開発者側の視点でシステムの設計を行います。
この詳細設計の工程でプログラムの仕様がきれいに書かれていると、どんなプログラマーが対応しても品質に差の生じないシステムを実装できます。
システムを開発する
次は、設計工程で作成した設計書の内容をシステムへと落とし込んでいく開発作業です。コーディング基準に従い、指定されたプログラミング言語でシステムを構築します。コードを書いた後はコードレビューを行い、必要に応じてデバッグをするなど、顧客が求めているシステムを実現していきます。
完成したシステムをテストする
システム開発が終わったら、適切に動作するか、不具合が起きないか、といった視点でテストを行います。品質の低いシステムを納品してしまうと、顧客満足度に影響するため、納品前にテストを行って品質をチェックすることが重要です。
テスト業務は目的に合わせて、主に4つ存在します。作成したモジュールが設計書で要求された機能を満たしているかを検証する単体テスト、複数のモジュールを組み合わせて検証する結合テスト、システムが全体として要求された機能や性能を満たしているかを検証するシステムテスト、最後に実際の業務の流れに沿って利用してみて問題なく動作するかを検証する運用テストを行います。
これらのテストにて不具合が発生した場合は、速やかに修正して改善します。
納品後、運用・保守を行う
SI案件はシステムを納品して終了するわけではありません。システムの起動や停止、そして日々動かしていく作業であり、納品後、運転状況の監視、CPUやメモリの利用状況を確認するなどシステム資源の監視も行います。
また、保守作業ではシステムの障害が起きた際の緊急対応や、顧客からの追加機能の要望に伴うプログラムやデータの改修を行います。
SIによって実現されているシステムの具体例

「SI」と聞いても、具体的にどのような案件があるのかイメージが湧かない人も少なくないでしょう。私たちが生活をする中で、SIが関わっているシステムは多々あります。
そこで、ここではSIが関わっているシステムの具体例を4つ紹介します。
銀行のオンライン取引分野
現代では、自分が口座を開設した銀行の支店以外でもお金を引き出しや預け入れができたり、他の金融機関のATMやコンビニATMなどでも取引ができます。また、ネットバンキング機能がある銀行の場合、スマホやパソコンがあれば、時間や場所を選ばずにオンライン上で銀行取引が可能です。
このように、自由に銀行の取引ができるようになった背景には、SIの存在があります。口座情報が紐づくようシステムを開発し、金融機関同士でのネットワークを構築したことで、オンライン取引ができるようになっています。また、他銀行のATMやネットバンキングでも正常に取引ができるのは、SIerが適切に保守しているためです。
キャッシュレス決済分野
キャッシュレス決済には、クレジットカードやプリペイドカードだけではなく、近年は電子マネーやQRコード、スマートフォンのタッチによる決済方法が登場しています。これらを実現しているのもSIです。
キャッシュレス決済は現金以外で支払うため、消費者の口座に紐づいて自動でお金を取引できる仕組みが必要です。そして、消費者の支払額を、店舗側に振り込む必要もあります。そこでSIerがこれらのシステムやネットワークを構築し、適切に運用することでキャッシュレス決済が実現しています。
製造業分野
製造業では、複数の機器やロボットを活用しなければ業務を回せません。それらを制御したりデータを蓄積したりするためのシステムも必要です。また、生産管理や不良品検出、在庫管理や配送管理など、プロセスに合わせて複数のシステムを使い分ける必要があります。
そのため、ハードウェアとソフトウェアどちらも一貫して手掛けられるSIerの腕の見せ所です。機器とシステムを同期させたり、複数のシステムを連携したりすることで、製造現場の効率化を実現します。
医療・ヘルスケア分野
医療やヘルスケアの分野でも、さまざまなシステムが取り入れられています。病院に行かなくても受診できるオンライン診療、診療記録を電子化した電子カルテ、スマホで服薬履歴を確認できる電子お薬手帳など多岐にわたります。
また、医療機器とシステムをつなぎ、患者データを可視化する仕組みもあります。このように、患者に関わる多様なデータを連携させて診療や治療に活かすため、要件定義から開発、運用まで一貫して行うSIの存在があります。
フリーランスエンジニアの案件紹介サービスTECH STOCKには、金融、製造、通信など様々な分野のSI案件が多数ございます。高単価・上場企業・即アサイン可能など、スキルや希望にマッチする案件をご紹介します。フリーランスになって年収アップを狙うならTECH STOCKにお任せください。
SI案件の現状と将来性

SI案件に携わるうえで理解しておきたいのが、現状と将来性です。SI案件が現在どのような課題を抱えているのか、今後伸びしろはあるのか、といった視点から解説します。
SI案件の現状の課題1:多重下請け構造
SI案件は、下請け構造となっていることが一般的です。また、階層が多層になっていることも特徴で、要件定義・設計などの上流工程や顧客(発注者)とのやり取りは一次請けSIerが担当し、開発・テスト・運用などの下流工程は二次請けSIerや三次請けSIerが担当します。
一社で上流工程から下流工程まですべてを網羅している場合もありますが、業務効率化や人的リソースの観点から下請けに依頼してプロジェクトを進めていくことが多く見られます。
多重下請け構造なので、上流工程を担うSIerと下流工程を任されるSIerでは業務内容が大きく異なります。もちろん下請けにいくほどコストは削られていくため、従業員の年収にも影響が出るでしょう。
SI案件の現状の課題2:慢性的な人手不足
SI案件に限った話ではありませんが、IT人材が慢性的な人手不足に陥っていることも現状の課題です。経済産業省が発表した「DXレポート(※)」では、2015年の時点ですでに17万人も不足しているとされています。
SI案件は複数の工程があるうえに、継続的に運用・保守をしていく必要があり、多くの人材が必要です。そのため、IT人材の人手不足は、SI案件を円滑に進めていくうえで大きな課題となっています。
※参考:経済産業省『DXレポート』
SI案件の今後の展望1:DX化の促進
近年のビジネスにおけるキーワードが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。ビジネスにデジタルを取り入れ、企業成長につなげる取組みを指します。
政府が主体となって企業のDX化を推進している中、今後さらにDX化が進み、多くの企業で新規システムの導入やシステムの刷新などが行われると予測されます。また、デジタルを活用した新たなビジネスモデルも登場するでしょう。
したがって、今後SI案件は増加していくことが予想されます。
SI案件の今後の展望2:人手不足による市場価値の向上
2025年には、約43万人までIT人材が不足すると発表されています(※)。そのためSI案件に携われる人材は貴重となり、市場での価値が向上すると見込めます。
慢性的な人手不足を逆手にとり、早いうちからSI案件に携わって知識や経験を積んでおくことで、今後拡大していくSI案件市場での需要が高まるでしょう。
※参考:経済産業省『DXレポート』
SI案件に携わるメリット

SI案件は今後の拡大が予測される分野です。そのため、前章で解説したように、今のうちからSI案件の経験を積んでおくことで、自身の市場価値向上につながるでしょう。
また、その他にもSI案件に携わるメリットがいくつかあります。
- さまざまなプロジェクトに関われる
- 汎用性の高いスキルが身につく
- 世の中の役に立つ
- 安定して仕事を得られることが多い
上記のメリットについて、一つずつ詳しく解説します。
さまざまなプロジェクトに関われる
事例として紹介した「銀行のオンライン取引」や「キャッシュレス決済」などのように、分野にこだわらずにシステムを開発することが多く、さまざまな業界の仕事に携わります。
一般的なSI案件は顧客が企業となるBtoBビジネスですが、まれに政府や地方自治体が顧客となるBtoGビジネスの場合もあります。そのため、社会の仕組みが理解できるようになったり、多くの人物と関われるため自身の経験にもつながるというメリットがあります。
汎用性の高いスキルが身につく
SI案件は、システムの要件定義から運用のIT系業務以外にも多くの業務を行うため、以下のようなさまざまなスキルを身に着けることもできます。
- 社内の折衝
- プロジェクトマネジメント
- スケジュール管理
- トラブル対応
- 資料作成
上記のように、SI案件に携わることでIT技術以外のスキルアップにもつながるでしょう。
世の中の役に立つ
金融、製造、医療などさまざまな分野のSI案件があります。どれも、顧客の課題を解決できるだけでなく、広い視野で見ると世の中に役立つシステムとなっています。
多くの人々の生活を支えたり、利便性を向上させたりするシステムを開発できるため、達成感や満足感を得られるでしょう。仕事を通じて世の中の役に立ちたい人は、SI案件に携わることがおすすめです。
安定して仕事を得られることが多い
SI業界はBtoBであり、大規模なプロジェクトを取り扱う事が多いため、安定して仕事を得られやすいです。特に、官公庁や金融、医療機関のシステム開発を多く受けている企業は仕事が途絶える可能性が低いでしょう。
また、IT、AIが話題になっており、システム開発の需要が高まっていることも要因となっています。
フリーランスエンジニアの案件紹介サービスTECH STOCKには、金融業界、製造業界、通信業界などのSI案件が多数ございます。高単価・上場企業・即アサイン可能など、スキルや希望にマッチする案件をご紹介します。継続した参画ももちろん可能です。
まとめ
SIは金融や製造、医療など多様な分野で導入されています。今後も需要は高い状態が続くと予想されるため、SI案件に携わることで多くの経験を積むことができるでしょう。
SI案件に携わるためには、SIerとして勤務するか、フリーランスエンジニアとしてSI案件に参画するか、どちらかです。TechStockではフリーランスエンジニア向けのSI案件を豊富に紹介しているため、気になる方はぜひお問い合わせください。