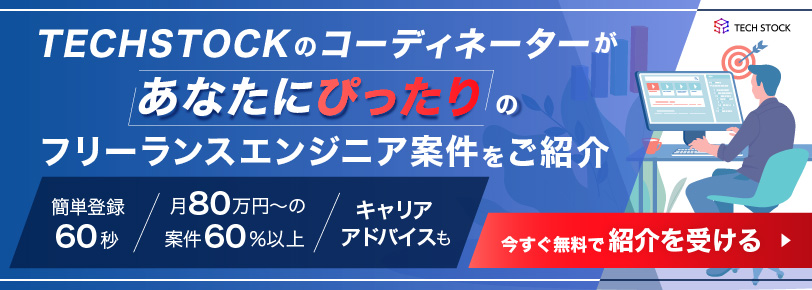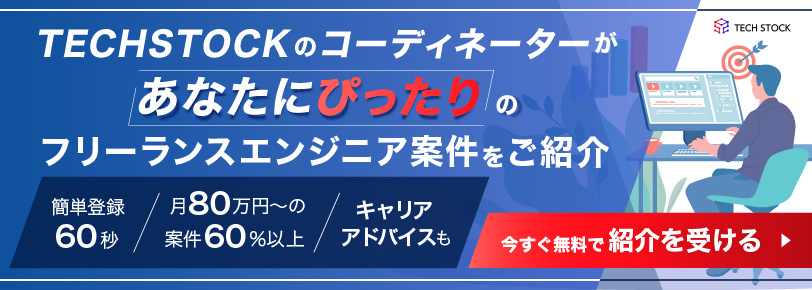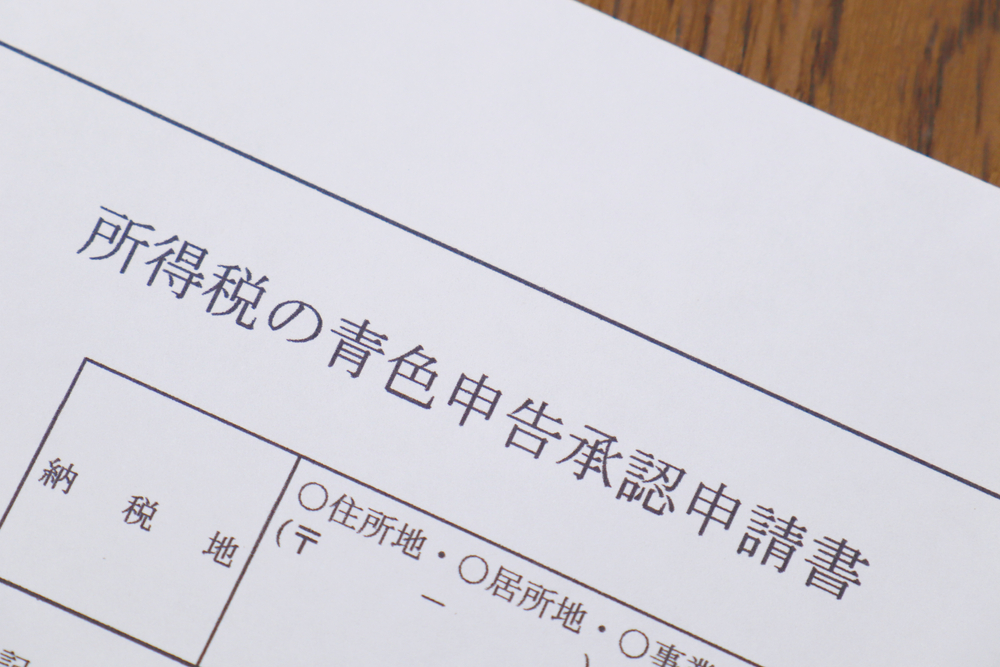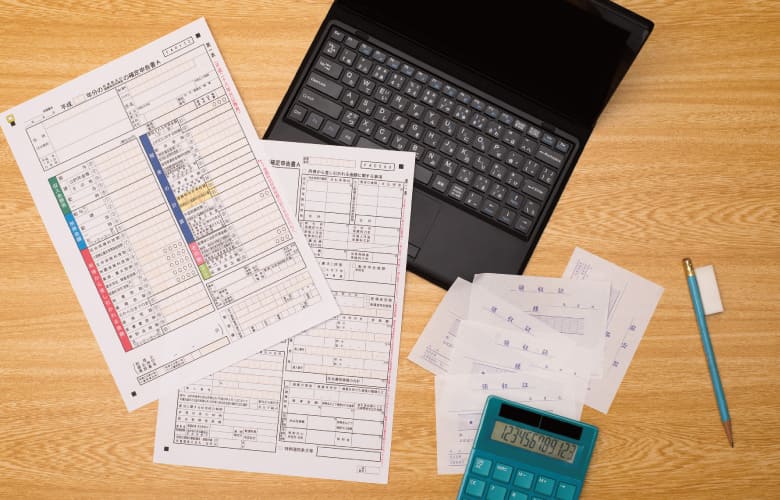税務調査は個人でいくらから?対象になりやすい人の特徴や対策を解説
税務調査は、適正な納税を確保するために行われる重要な手続きです。
しかし、個人事業主やフリーランスの中には、「どのような基準で調査対象となるのか」「どのくらいの収入があると税務署の目に留まりやすいのか」と不安に思う方もいるでしょう。
本記事では、税務調査がどのような基準で行われるのか、どの程度の年収から対象になりやすくなるか、調査はどのような観点でチェックするのかなどを詳しく解説します。
さらに、税務調査を回避するための対策や、調査が入った際の適切な対応方法についてもご紹介します。適切な税務申告を行い、無用なリスクを避けるための知識を身につけましょう。

税務調査とは?

税務調査とは、納税者が税金を適切に申告したうえで納税しているかを確認するために税務署が実施している調査です。法人だけでなく個人事業主やフリーランスも対象になり、申告内容の整合性や法令違反の有無がチェックされます。
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、任意調査は事前通知される場合がほとんどです。一方、強制調査は脱税の疑いが強い場合に実施され、裁判の令状に基づいて実施されます。
次のような場合は、税務調査の対象になる可能性があるため注意が必要です。
- 売上や経費の不自然な変動
- 長期間の無申告
- 現金取引が多い業種(飲食店・美容業など)
適切な申告と帳簿管理を徹底することで、税務調査を回避するための対策となります。
税務調査はいくらから来る?個人事業主が対象となる基準

税務調査が実際にどの程度の年収・売上で実施されるのかについては、明確な基準が定められているわけではありません。ここでは、個人事業主が税務調査を受ける確率や税務調査の対象となりやすい年収の目安について詳しく解説します。
フリーランスエンジニアの案件紹介サービスTECH STOCKでは、税理士や社労士の紹介も行っております。フリーランスの税務調査にお悩みでしたら、TECH STOCKのコーディネーターにご相談ください。
TECH STOCKはフリーランス・ITエンジニアのための案件紹介サイトです
個人事業主が税務調査に入られる確率
個人事業主が税務調査を受ける確率は0.5%〜1%とされています。
令和3年度のデータ(※)によると、個人の所得税の税務調査は約3.1万件実施されました。一方で、同年度に確定申告を行った個人の数は656.9万人であり、確率としては決して高くありません。
しかしながら、申告内容に不審点がある場合や現金取引が多い業種に該当する場合、調査対象になる可能性は高まります。特に、売上が急増したケースや過去に税務指摘を受けた事業者は注意しなければなりません。日頃から正確な帳簿管理を行い、申告内容に誤りがないようにするのが大切です。
税務調査の対象となる年収の目安
個人事業主の場合、課税売上高が1,000万円を超えるとインボイス登録を行っていなくても消費税の課税対象となるため、税務調査の対象になりやすい傾向があります。
ただし、課税売上高が1,000万円未満であっても、次のようなケースでは調査対象になる可能性があります。
- 不自然な経費の計上
- 所得の申告漏れ
- 過去に税務調査を受けた経験がある
いずれの場合も、正確な帳簿管理と適切な申告が重要です。
7年以上税務調査が来ない場合でも安心できない理由
税務調査は通常、5年から7年に一度行われる場合が多いとされています。しかし、7年以上税務調査がないからといって安心するのは危険です。税務署は過去7年分の申告内容をさかのぼって調査する権限を持っており、不審な点が見つかれば突然税務調査が入る可能性もあります。
また、税務調査されやすい業種や高額な経費を計上している事業者は、長期間税務調査がなかったとしても、突然調査対象となる可能性があります。
さらに、近年は税務署のAI分析技術が進化し、不審な申告を自動的にピックアップするシステムが強化されているため、これまで税務調査を受けていないからといって油断するのは危険です。適切な申告を続けるのが、調査を未然に防ぐ対策となります。
申告内容に不自然な点があると調査の対象になりやすい
申告内容に不自然な点があると、税務調査の対象になる可能性が高まります。例えば、課税売上高が毎年1,000万円近くで推移している場合、消費税の課税逃れを目的とした過少申告を疑われるかもしれません。
また、売上と経費のバランスが極端に不自然である場合や、前年と比較して大きく変動している場合も、税務署が不審に思う理由となります。特定の月だけ売上が大幅に高い、もしくは極端に経費が増えているなどの傾向がある場合も注意が必要です。
税務調査を回避するためには、日頃から正確な帳簿管理を行い、適切な申告を徹底するのが非常に重要です。
実際に税務調査が来た場合の流れ

税務調査は基本的に事前通知がありますが、業種や状況によっては突然の訪問調査が行われる可能性もあります。調査の目的は、申告内容が適正かどうかを確認することです。
ここでは、税務調査の基本的な流れや事前通知の内容について解説します。事前に把握し、適切に対応できるよう準備しておきましょう。
税務署からの事前通知
通常、税務調査の数週間前に税務署から調査日程や対象となる期間、必要書類などの事前通知があります。事前通知を受けたら、通知の内容をよく確認し、スケジュール調整や必要書類の準備などを進めましょう。可能であれば税理士に相談して、事前に適切な準備をしておくことで、調査当日もスムーズな対応が可能です。
また、通知方法は電話または書面が一般的ですが、場合によっては事前の連絡なしに突然調査が行われることもあります。特に、脱税の疑いが強い場合や過去に税務調査で重大な指摘を受けたことがある場合は、無予告で調査が実施される可能性が高くなります。
日程と場所の調整
税務調査の日程や場所は、事前通知の際に指定されますが、都合の悪い場合には税務署に連絡して変更の相談をすることも可能です。通常、調査は事業所や自宅で行われますが、必要に応じて税務署内で行われる場合もあります。
税務調査では、帳簿や契約書、領収書などの管理状況が重要視されるため、事前に必要書類を整理しておくのも大切です。しっかり準備をしておくことで、調査がスムーズに進み、不必要な指摘を受けるリスクを減らせます。
必要書類の準備
税務調査では、申告内容の正確性を確認するためにさまざまな書類の提出が求められます。
主に必要とされる書類は、次のとおりです。
- 総勘定元帳
- 売上や経費の帳簿・領収書
- 銀行通帳
- 契約書や請求書
- 領収書やレシートの原本
特に、経費の正当性を示す書類の管理が重要です。領収書がない場合でも、クレジットカードの利用明細や振込記録などで支払いの証拠を示せる場合があります。
ただし、消費税の申告がある場合には、クレジットカードの利用明細や振込記録だけでは証拠として不十分です。そのため、必ず領収書やレシートも保管しておく必要があります。
事前に必要な書類を準備しておけば、税務調査への対応がスムーズになり、不必要な指摘を受けるリスクも軽減されます。
税務調査当日の対応
調査当日は、税務署の職員が事業所や自宅を訪問し、帳簿や取引内容の確認を行います。
調査官の質問には正直に答えるのが重要ですが、不明点がある場合はその場で即答せず、「後日確認して回答します」と伝えるのも適切な対応です。早く終わらせようと不適切な対応や曖昧な返答をすると、かえって調査が長引く恐れがあるため注意しましょう。
また、税務調査当日に税理士へ立ち合いを依頼すれば、調査官とのやり取りをスムーズに進められるため不要な誤解を避けられます。
税務調査後に通知が届く
税務調査が終了すると、調査結果にもとづき税務署から指摘事項が通知されます。問題がなければ「更正決定等をすべきと認められない通知書」が送付され、その後の追加対応は不要です。
一方で、申告内容に誤りや修正が必要な場合は、「修正申告」や「更正通知」が発行されます。修正が求められた場合は、速やかに対応し、必要に応じて税理士に相談するのもおすすめです。
内容に異議がある場合は、税務署に異議申し立てを行うのも可能ですが、申し立てには期限が定められている点に注意が必要です。適切に対応すれば、ペナルティが発生した場合でも最小限に抑えられ、今後の申告ミスを防げます。
税務調査が入りやすい個人事業主の特徴

税務調査は、特定の条件を満たす個人事業主に対して実施されやすい傾向があります。
特に、申告内容に不審な点がある場合や、現金取引が多い業種などは税務署のチェックが入りやすいため注意が必要です。ここでは、個人事業主のなかでも税務調査の対象になりやすい人の特徴について解説します。
現金取引が多い業種は特に注意
飲食業や小売業など、現金での取引が多い業種は、税務署のチェックが特に厳しくなります。現金売上は記録が残りにくく、申告漏れや売上の過少申告が疑われる場合が多いためです。
税務調査では、売上の計上方法や経費の使い方を重点的に確認します。そのため、売上を正確に記録し、領収書や帳簿を適切に管理するのが非常に重要です。
現金取引が多い業種では、不必要な税務調査を避けるための方法として、POSレジや会計ソフトなどの導入も効果的です。取引の記録を明確に残すことで、調査対象となるリスクを軽減できます。
売上や利益が急増・急減すると調査の対象になりやすくなる
前年と比べて売上や利益が急増または急減した場合、税務署はその理由を確認するために調査を行う場合があります。特に、売上の急増があった場合、未申告の収入があるのではないかと疑われる可能性があるため注意が必要です。
また、急激な売上減少がある場合も、架空経費の計上や意図的な赤字計上を疑われる可能性があるでしょう。事業の成長過程における売上や利益の変動は、税務署にとっては調査対象となる要因にもなりえます。取引記録や契約書を明確に残し、税務署に説明できるよう準備しておくのが大切です。
経費の計上が適正でない場合
事業に関係のない支出を経費として計上すると、不正な申告と見なされ税務調査の対象になる可能性が高まります。例えば、個人的な買い物や家族旅行の費用を事業経費として処理するケースが該当します。
また、事業に関連している経費であっても、領収書や請求書がない場合は経費として認められない可能性が高いです。正しく経費を計上し、すべての取引記録を保存しておくことが、税務調査のリスクを軽減するために重要です。
無申告や申告の遅延を繰り返している
確定申告を行わない、あるいは申告期限を過ぎてからの申告が続くと、税務署の信用を失い、税務調査の対象となる可能性が高まります。特に、売上があるにもかかわらず無申告が続く場合、税務署は意図的な脱税を疑うかもしれません。
また、申告期限を過ぎてからの申告をする場合、延滞税や加算税が発生するため、経済的な負担も大きくなるでしょう。税務調査を避けるためにも、期限内に正しく申告し、日々の帳簿管理を適切に行うことが重要です。
税務調査を避けるための対策

税務調査を回避するためには、日々の徹底した帳簿管理と適切な申告が重要です。特に、電子帳簿の導入や税理士への依頼など、正確な記録と信頼性の高い手続きを意識しておけば、調査リスクを軽減できます。
ここでは、5つの具体的な対策を解説します。
電子帳簿保存法へ対応する
電子帳簿保存法に対応することで、税務調査時のトラブルを防げます。PDFやスキャンデータといった電子データは、一定の条件化で適切に保存・管理する必要があります。データの改ざん防止措置として、修正履歴を残せるシステムを導入するのもおすすめです。
また、取引情報を迅速に確認できる検索機能を備えた会計ソフトを活用することで、税務署からの問い合わせにも素早く対応できます。電子帳簿保存法に適切に対応しておくことで、税務署からの信頼を得られやすくなり、税務調査のリスクを軽減できます。
税理士に確定申告を依頼する
税理士に確定申告を依頼することで、申告の正確性が向上し、税務調査のリスクを抑えられます。税理士が作成する申告書には専門的なチェックが入るため、申告漏れや計上ミスの防止に効果的です。税理士の署名が入った申告書は、税務署からの信頼を得やすくなる傾向があります。
また、署名だけでなく税理士が扱える「書面添付制度」を活用し、申告書に保証書のような書面を添付することで、さらに高い信頼を得やすくなります。税理士に依頼すれば、税務署からの問い合わせにも適切に対応できるため、個人で対応するよりも安心です。
税理士への報酬は経費として計上できる点も考慮すると、費用対効果の面でも十分なメリットがあります。
フリーランスエンジニアの案件紹介サービスTECH STOCKでは、税理士や社労士の紹介も行っております。フリーランスの税金対策にお悩みでしたら、TECH STOCKのコーディネーターにご相談ください。
TECH STOCKはフリーランス・ITエンジニアのための案件紹介サイトです
日々の帳簿を正確に記録する
日々の取引を正確に記録し、領収書や請求書を適切に保管することは、税務調査を回避するための基本的な対策です。
売上や経費の記録に誤りがあると、不正申告を疑われる可能性があります。特に現金取引が多い業種では、売上の過少申告を疑われる可能性があるため、細かな記帳を心がけるのが重要です。例えば、デジタル会計ソフトを活用すれば、記帳ミスを減らして取引履歴を正確に管理できます。
売上や収入を適切に申告する
正確な税務申告は、事業を運営するうえで必要不可欠です。売上を意図的に過少申告すると、発覚した際に追徴課税や重加算税が科されるリスクがあります。
特に、消費税の課税売上高1,000万円前後の事業者は、免税事業者であり続けるために売上を調整するケースがあるため、税務署のチェックが厳しくなる傾向があります。
また、報酬として受け取った所得も、漏れなく申告しなければなりません。適切な申告を行い、税務署から「申告内容について問い合わせを受ける」「加算税の支払いが発生する」などのリスクを最小限に抑えましょう。
税務署からの問い合わせには誠実に対応する
税務署からの問い合わせには、誠実かつ迅速に対応することが重要です。無視や曖昧な回答は不信感を生み、税務調査の可能性を高めてしまいます。
不審点を早期に解消させるためには、問い合わせ内容に対して正確な記録を提示し、事実にもとづいた回答をするのが非常に大切です。
また、必要に応じて税理士に相談し、適切な対応方法を確認するのもおすすめです。税務署からの問い合わせは、必ずしも税務調査につながるわけではありません。冷静かつ適切に対応して、不要な調査を未然に防ぐことが大切です。
領収書がないと税務調査で経費は否認される?

税務調査では、経費の正当性を証明するために領収書の提出が求められます。
しかし、領収書がない場合でも、経費として認められる場合があるのも事実です。例えば、銀行振込の明細書やクレジットカードの利用履歴があれば、取引の事実を示す証拠になります。また、取引先とのメールのやり取りや契約書、納品書なども経費の証明として有効です。
ただし、銀行振込の明細書やクレジットカードの利用履歴があっても、税務署の判断によっては経費と認められないケースもあります。そのため、できる限り領収書を保存しておくことが重要です。
特に現金での支払いは証拠が残りにくいため注意が必要です。クレジットカードや銀行振込を活用することで、取引の証明がしやすくなります。経費処理の透明性を高めておけば、税務調査時のリスクを低減可能です。
まとめ
税務調査は、税務署が申告内容の正確性を確認するために行うものです。特に、課税売上高が1,000万前後を推移している場合や申告に不自然な点がある場合は、税務調査の対象となりやすい傾向があります。
個人事業主であっても、売上や経費の記録は正確に管理したうえで、適切な申告をしなければなりません。また、税務調査のリスクを避けるためには、電子帳簿保存法の活用や税理士への依頼も効果的です。
税務調査が入った場合も、冷静に対応し、必要な資料を適切に提出することで、リスクを最小限に抑えられるため、落ち着いて対処しましょう。