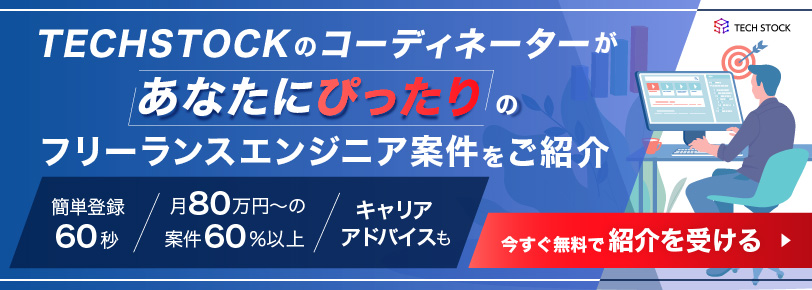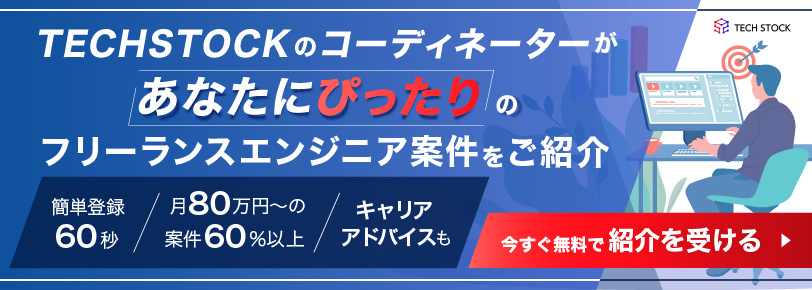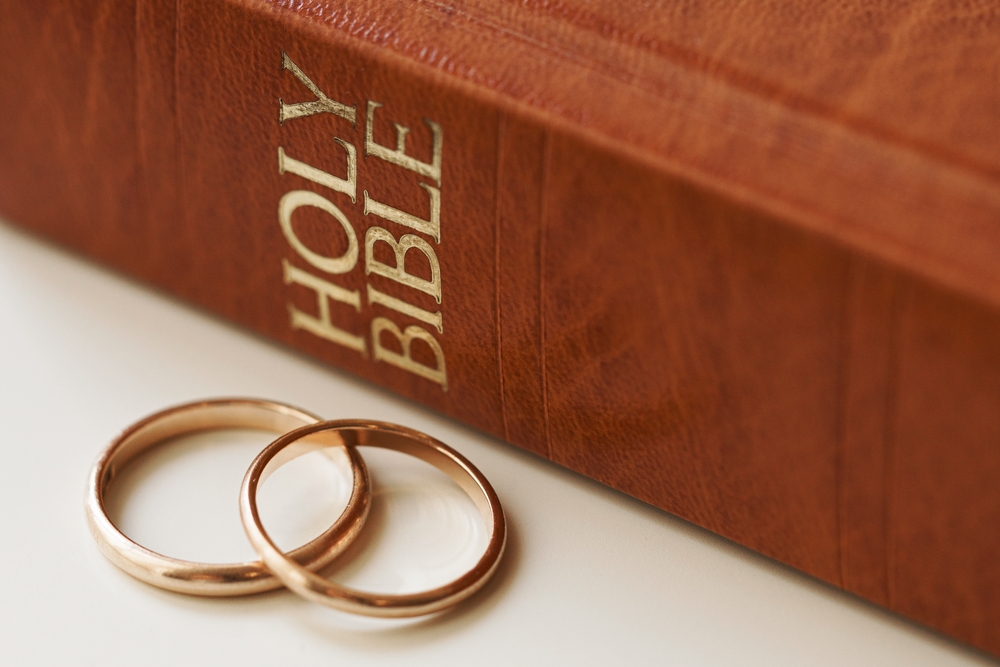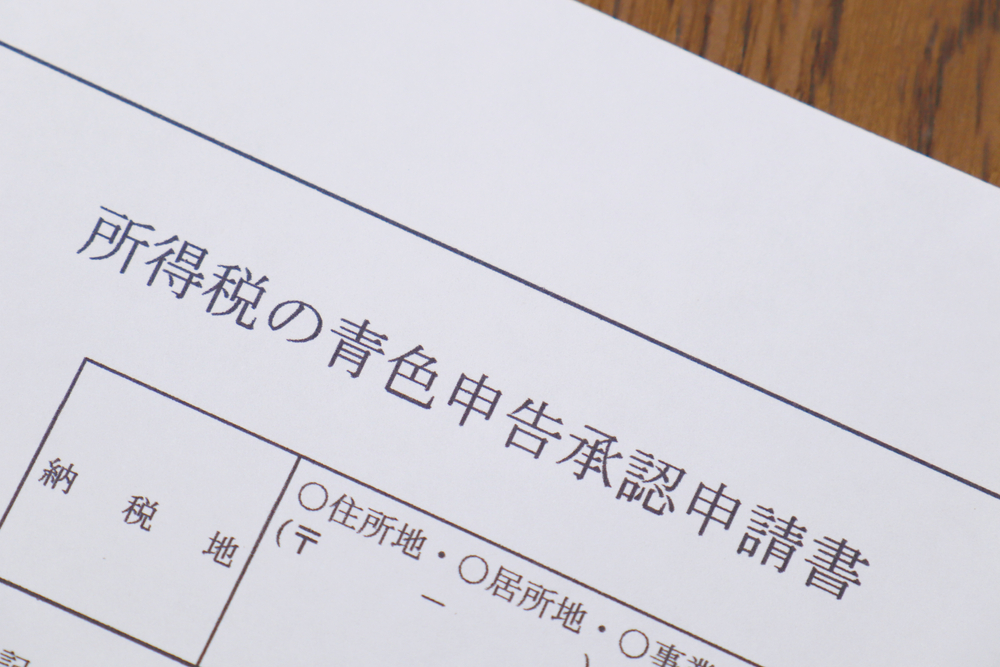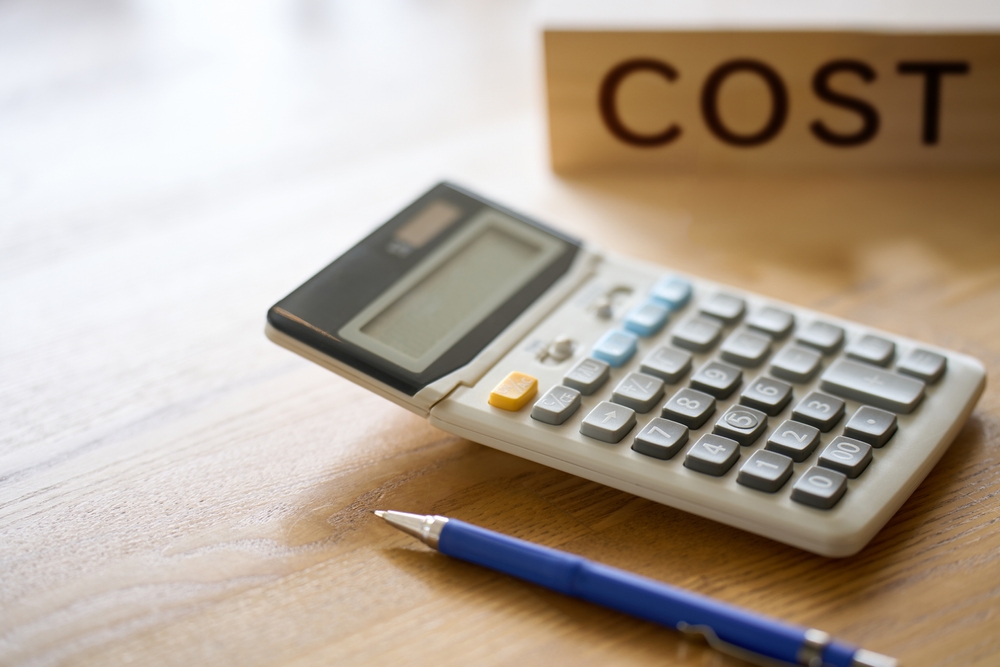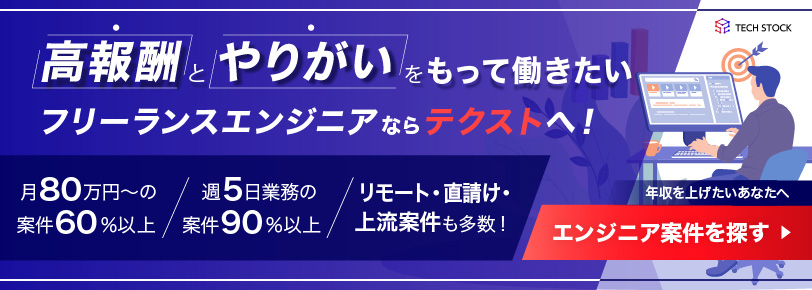フリーランスになったら健康保険はどうする?年収別保険料の目安や加入手続を解説
社会保険とは、医療費の自己負担の軽減や退職後の生活資金を支えるための保障制度のことです。しかし、会社員向けの社会保険制度は企業に在籍していることが前提であり、フリーランスは対象外となります。
このように、フリーランスと会社員では、利用できる保険制度が異なります。そのため、フリーランスになって日が浅い方や、フリーランス転向を検討中の方にとって、保険などの社会的な手続きは不安要素の一つといえるでしょう。
本記事ではフリーランスが加入できる健康保険について、その種類や年収別の費用の目安、手続きなどについて説明します。保険に関する不安を持つフリーランスと志望者の方はお役立てください。

フリーランスと会社員の公的医療保険制度の違い

フリーランスと会社員が利用する公的医療保険制度は、基本的に異なります。フリーランスは一般的に「国民健康保険」を利用し、会社員は企業が加入している社会保険の健康保険に自動的に加入します。
なお、フリーランスの場合については一部例外があるため、本記事内の「フリーランスが加入できる健康保険の種類について」の項をご参照ください。
以下は、国民健康保険と社会保険の健康保険の特徴をまとめたものです。
| 国民健康保険 | 社会保険の健康保険 | |
| 加入対象者 | フリーランス(自営業者) 無職など |
会社員 条件を満たす短時間労働者 |
| 運営者 | 市区町村などの自治体 国民健康保険組合 |
企業が加入している社会保険団体 |
| 保険料負担 | 被保険者が全額 | 被保険者と組織が折半 |
| 保険料の算出方法 | 自治体:確定申告時の所得より自治体ごとの保険料率で算出 国民健康組合:定額など |
前年度収入より標準報酬月額を決定して算出 |
| 扶養家族制度 | なし | あり |
国民健康保険
国民健康保険制度は、ほかの医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入していない住民を対象とした医療保険制度です。略して「国保」とも呼ばれ、企業などの組織に属していないフリーランスや無職の方でも加入できます。日本国内に在住している場合、外国籍の方も対象です。
市区町村などの自治体が保険者となる国民健康保険と、業種や地域ごとに組織される国民健康保険組合で構成されます。市区町村が保険者となる国民健康保険の場合、在住する地域の保険に加入でき、手続きは通常、各自治体の役所の窓口で行います。
社会保険の健康保険
社会保険とは、企業に所属する正社員や契約社員のほか、一定の条件を満たすパート・アルバイトなどの短時間労働者も加入できる公的な保険制度です。すべての法人および従業員が5人以上在籍している個人事業所は、健康保険と厚生年金保険への加入義務があるため、正社員は一部の例外を除き社会保険に加入することになります。
社会保険は、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」の5種類で構成されています。保険料の負担は所属企業と雇用者が折半します。社会保険の健康保険の保険者には、健康保険組合と全国健康保険協会(協会けんぽ)があり、出産手当金や傷病手当金制度なども設けられています。
なぜフリーランスも保険に入らねばならないか

フリーランスは組織に所属しない働き方ですが、なぜ保険に加入する必要があるのでしょうか。以下では、フリーランスにおける健康保険制度による加入義務と、未加入の場合に生じる問題について説明します。
TECH STOCKは案件紹介だけでなく、フリーランスとして安心してご就業できるように税務・法務などもサポートしております。働き方を変えるならTECH STOCKにお任せください。
健康保険加入は義務
日本では国民皆保険制度が運用されており、国民は何らかの公的医療保険への加入が義務付けられています。国民皆保険とは、国民全員を公的医療保険で保障し、自由に医療機関を選択できることや比較的安い診察料で高度な治療を受けられることを実現するための制度です。
フリーランスの場合、例外を除き国民健康保険への加入が義務付けられています。なお、例外として挙げられるのは、社会保険の任意継続、家族社会保険の被扶養者としての加入、健康保険組合の利用です。
健康保険に加入しなかった場合に起こる問題
前述の通り、健康保険への加入は義務です。もし加入をしない、つまり保険料の支払いがない場合には、督促の連絡が入ります。また、納期限までに完納されなかった場合には延滞金が発生し、納付能力があるにもかかわらず納付を行わない場合には、財産の差し押さえなどの措置が取られることもあります。
フリーランスが加入できる健康保険の種類について

特に会社員からフリーランスへの転身を検討している場合、健康保険の比較検討をすることが望ましいでしょう。ここでは、フリーランスが加入できる健康保険の種類について紹介します。
TECH STOCKはフリーランス・ITエンジニアの方に案件をご紹介して20年以上、全登録者52,000名以上の案件紹介サービスです。スキルや希望にマッチする案件をご紹介するだけでなく、税理士や社労士の紹介、アサイン後のフォローアップなど、案件紹介以外のフォローも充実しております。
国民健康保険
国民健康保険は市区町村などの自治体が運営する健康保険であり、フリーランスが原則として加入する公的医療保険です。詳細については、各自治体のホームページなどで確認ください。ご参考までに、大阪市の公式ホームページのリンクはこちらです。
厚生労働省が発表した「国民健康保険実態調査(令和5年度)」によると、国民健康保険に加入している全世帯数が約1,765万世帯、このうち、市区町村の国民保険加入は1,624万世帯でした。また、国民健康保険加入世帯のうち、「その他自営業」が17.3%を占めており、この数字から約280万の自営業者を世帯主とする世帯が加入していると推定できます。
一方、「令和4年就業構造基本調査の結果」によると、自営業者数は511万人でした。世帯数と人数のため単純には比較できないものの、自営業者の半数以上が国民健康保険に加入していると推測されます。
独立前の社会保険の任意継続
会社員からフリーランスになる場合、会社員として加入していた社会保険を継続して利用できる制度(任意継続)があります。会社員からフリーランスに転向しても同等の条件で保険を利用できるため、主に以下のようなメリットが期待できます。
- 扶養家族制度が継続できる
- 保険組合の独自の給付が受けられる
- 収入額によっては国民健康保険よりも保険料を抑えられる
- 健康保険料を確定申告時に所得控除として申請できる
ただし、社会保険の任意継続を利用する場合、注意点もあります。
主な注意点については、本記事の3章5項目で解説しています。
家族の扶養として社会保険に加入
家族が会社員として働いており社会保険に加入している場合、その扶養家族として社会保険に加入することもフリーランスの選択肢の一つです。状況によって異なるものの、メリットと加入条件などを考慮して検討しましょう。
扶養家族として社会保険に加入する場合には、下記のメリットがあります。
- 医療保険、年金は被保険者分のみで済むため、社会保険料を抑えられる
- 保険料は被保険者の控除対象となり、税の負担が軽減できる
なお、社会保険の扶養控除対象は、下記の条件を満たしている場合です。
- 被保険者により生計を維持されている
- 年間収入が130万円を満たしていない(※例外として、対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる障がい者の場合、180万円未満)
業種別などの国民健康保険組合に加入
業種や所属地域ごとに国民健康保険組合を設けている場合、条件を満たしていれば、フリーランスと自営業者は市区町村の国民健康保険の代わりとして加入することが可能です。ただし、各国民健康保険組合により条件や保険料が異なるため、その点を注意しましょう。主なメリットとして以下の点が挙げられます。
- 保険料は定額であることが多く、高収入の場合は割安になることがある
- 市区町村の国民健康保険より保険料を抑えられる場合がある
- それぞれの業種ごとに作られているため、組合ごとにきめ細やかな運用が可能
国民健康保険組合の例として、下記が挙げられます。
- 文芸、美術および著作活動に従事者向け:文芸美術国民健康保険組合
- 土木建築業:全国土木建築国民健康保険組合
(一社)全協ホームページにて一覧を参照できます。※全協:全国健康保険組合協会
各保険のメリット・デメリット比較
本記事内で紹介するフリーランスが選択できる健康保険4種について、メリットとデメリット、注意点をまとめました。健康保険を検討する際にお役立てください。
| メリット | デメリット、注意点 | |
| 市区町村の 国民健康保険 |
・国内の居住者が加入可能 | ・保険料は他の保険のほうが安い場合がある |
| 社会保険の 任意継続 |
・扶養家族制度が継続できる ・保険組合の独自給付が受けられる ・収入額によっては国民健康保険よりも保険料を抑えられる ・保険料を確定申告時に経費として計上可能 |
・企業による保険料の半額負担はない ・加入期間は最大で2年 ・加入先の保険組合によって条件は異なる |
| 家族の社会保険の被扶養者 | ・医療保険、年金は被保険者分だけで済むため、社会保険料を抑えられる ・保険料が被保険者の控除対象となり、税負担の軽減が可能 |
・収入などに条件がある (同一の生計、収入130万円未満) |
| 国民健康 保険組合 |
・保険料は定額で、割安になる場合がある ・市区町村の国民健康保険よりも保険料を抑えられる場合がある |
・それぞれの国民健康保険組合により条件や保険料などは異なる |
国民健康保険の年収別保険料の目安

国民健康保険の保険料は、居住する市区町村によって異なります。基本的に所得に応じて高くなる料金体系となっています。
以下は所得に応じた保険料の例として、東京都新宿区の2024年(令和6年)の場合を、事業所得者の平均所得を抜粋しています。事業所得者の平均所得は「国税庁 令和5年申告所得税標本調査結果」によると483万円でした。
| 総所得金額など | 年間保険料 (※未就学児は32,800円) | 1か月あたりの保険料 (※未就学児は2,733円) | ||
| 介護なし (40~64歳以外) |
介護あり (40~64歳) |
介護なし (40~64歳以外) |
介護あり (40~64歳) |
|
| 0円 | 65,600円 | 82,100円 | 5,467円 | 6,842円 |
| 250,000円 | 65,600円 | 82,100円 | 5,467円 | 6,842円 |
| 500,000円 | 73,643円 | 91,655円 | 6,137円 | 7,638円 |
| 750,000円 | 102,368円 | 125,780円 | 8,531円 | 10,482円 |
| 1,000,000円 | 131,093円 | 159,905円 | 10,924円 | 13,325円 |
| 1,250,000円 | 159,818円 | 194,030円 | 13,318円 | 16,169円 |
| 1,500,000円 | 188,543円 | 228,155円 | 15,712円 | 19,013円 |
| 1,750,000円 | 217,268円 | 262,280円 | 18,106円 | 21,857円 |
| 2,000,000円 | 245,993円 | 296,405円 | 20,499円 | 24,700円 |
| 2,250,000円 | 274,718円 | 330,530円 | 22,893円 | 27,544円 |
| 2,500,000円 | 303,443円 | 364,655円 | 25,287円 | 30,388円 |
| 2,750,000円 | 332,168円 | 398,780円 | 27,681円 | 33,232円 |
| 3,000,000円 | 360,893円 | 432,905円 | 30,074円 | 36,075円 |
| 3,250,000円 | 389,618円 | 467,030円 | 32,468円 | 38,919円 |
| 3,500,000円 | 418,343円 | 501,155円 | 34,862円 | 41,763円 |
| 3,750,000円 | 447,068円 | 535,280円 | 37,256円 | 44,607円 |
| 4,000,000円 | 475,793円 | 569,405円 | 39,649円 | 47,450円 |
| 4,250,000円 | 504,518円 | 603,530円 | 42,043円 | 50,294円 |
| 4,500,000円 | 533,243円 | 637,655円 | 44,437円 | 53,138円 |
| 4,750,000円 | 561,968円 | 671,780円 | 46,831円 | 55,982円 |
| 5,000,000円 | 590,693円 | 705,905円 | 49,224円 | 58,825円 |
出典:新宿区|令和6年度 国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等) をもとに作成
国民健康保険加入手続きについて

ここでは、市区町村の国民健康保険に加入する場合の手続きの概要をご紹介します。以下の手続きは、会社員からフリーランスに転向する方を想定しています。お住まいの自治体によって詳細は異なるため、自治体の公式ホームページでご確認ください。
TECH STOCKは案件紹介だけでなく、フリーランスとして安心してご就業できるように税務・法務などもサポートしております。働き方を変えるならTECH STOCKにお任せください。
必要書類
会社員からフリーランスになる際の加入手続きとして、以下の書類が必要です。なお、転入など場合によって必要な書類は異なります。
- 健康保険の資格喪失証明書(退職証明書でも代用可能)
- 個人番号確認(例:マイナンバーカード、個人番号通知カード、住民票)および本人確認書類(例:運転免許証、パスポート、健康保険証)
個人番号については、マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の表示がある住民票にて確認可能です。マイナンバーカードが手元にあれば個人番号と本人確認が同時にでき、便利です。
申請期限
会社を退職してフリーランスになる場合、これまで加入していた健康保険などの資格を喪失した日(退職日)の翌日から14日以内に居住する市区町村の国民健康保険の窓口にて加入の届出をする必要があります。
申請期限に届出が間に合わない場合、下記の問題が発生します。
- 保険診療は、保険証または資格確認書の交付まで受けることができず、その間の医療費は全額自己負担
- 国民健康保険に加入した日の翌日からさかのぼって(最長で過去2年分)保険料が発生する
- 保険料の支払いがさかのぼって請求された場合、一度に数十万円の負担が生じる場合がある
申請方法
市区町村の国民健康保険の手続きは、役所(役場)の保険関連の窓口にて行うことができます。また、東京都千代田区や神奈川県大和市といった自治体では、オンラインや郵送での申請にも対応しています。申請方法の詳細については、居住する自治体の公式ホームページでご確認ください。
フリーランスが健康保険料を安く抑えるための方法

フリーランスとして働く場合、国民皆保険制度に従い公的医療保険への加入は義務であり、保険料の納付は必須です。自治体や健康保険組合の定めた所定のルールに従って支払うことが義務付けられています。
ただし、ある程度保険料を安く抑えられる場合もあります。以下では、フリーランスが国民健康保険料を安く抑えるための方法を紹介します。
TECH STOCKはでスキルや希望にマッチする案件をご紹介するだけでなく、税理士や社労士の紹介、アサイン後のフォローアップなど、案件紹介以外のフォローも充実しております。
適切に経費を計上して所得額を抑える
市区町村の国民健康保険の場合、保険料は前年の所得額から算出されます。つまり、所得が増えれば増えるほど、国民健康保険料も高くなるという料金体系です。
フリーランス(自営業)の場合の所得とは事業所得のことであり、収入から必要経費と仕入額を差し引いた金額のことです。この所得が住民税の課税対象額や保険料の算出基準にも使われます。所得は確定申告により最終的に決定し、計上した経費分は所得額から差し引くことが可能です。経費を適切に計上し、所得額を抑えることで保険料の算出対象額を減らすことができるため、国民健康保険料も抑えることができます。
フリーランスの経費として認められる範囲など、より詳しく知りたい方は下記の記事もご参照ください。
【税理士監修】フリーランスが経費で認められる支出は?確定申告のポイントも解説
なお、国民健康保険料は確定申告の際に所得控除の対象となるため、正しく申告することが重要です。
フリーランスの確定申告について、より詳しく知りたい方は、下記の記事もご参照ください。
【税理士監修】フリーランスの確定申告ガイド!手続&必要書類など徹底解説【2024年版】
免除・減免制度の利用
災害・失業・所得減少などの理由により国民健康保険料を納めることが難しい場合、自治体では保険料の免除や減免の制度を設けています。制度の有無や必要な手続き、利用条件などは各自治体の公式ホームページを確認し、窓口へ問い合わせもしてみましょう。なお、免除・減免制度の利用には所得制限がある場合が多いため、こちらの条件もご確認ください。
フリーランス向けの健康保険組合への加入
業種ごとに組織される国民健康保険組合に加入したほうが、自治体の国民健康保険より保険料が抑えらえる場合があります。各健康保険組合により保険料や加入条件は異なるため、組合のサイトなどからご確認ください。
以下のホームページから、一覧を確認できます。
(一社)全協ホームページ ※全協:全国健康保険組合協会
フリーランスの健康保険についてよくある質問と回答

フリーランスとして働く場合にも、ケガや病気に備えるためにも公的医療保険への加入は必須です。
前述の内容と被っている箇所がありますが、ここではフリーランスの加入する健康保険に関する、よくある質問とその回答をまとめました。フリーランスになって日が浅い方や、フリーランス転向を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
TECH STOCKは案件紹介だけでなく、フリーランスとして安心してご就業できるように税務・法務などもサポートしております。働き方を変えるならTECH STOCKにお任せください。
Q1:フリーランスは国民健康保険に加入する義務がありますか?
A1:国民皆保険制度のもと、日本に居住している方は公的医療保険制度への加入が義務付けられており、フリーランスの場合も同様です。全国の市区町村が保険者として国民健康保険を運営しているため、健康保険の選択肢がない場合には必ず国民健康保険に加入しましょう。
Q2:家族の扶養に入れる条件を教えてください
A2:家族が社会保険に加入している場合、一般的に下記の条件に該当していれば社会保険に被扶養者として加入することが可能です。
- 被保険者と生計を同一にしている
- 基本年間収入が130万円未満(※年齢や障がいの有無や程度によって条件が異なる場合があるため、詳細は社会保険組合にお問い合わせください)
なお、詳細については各社会保険組合などにお問い合わせください。
Q3:国民健康保険への加入はどのような手続きがありますか?
A3:市区町村の国民健康保険の場合、役所の医療保険関連(※)の窓口に赴き手続きすることができます。ケースにより必要な書類は異なりますが、会社員からフリーランスになる場合は下記の書類が必要です。
- 健康保険の資格喪失証明書
- 個人番号確認および本人確認書類
詳細は、各自治体のホームページなどでご確認ください。
※ 各自治体によって担当窓口名が異なるため、居住の自治体のホームページで窓口の正式名称をご確認ください。
Q4:国民健康保険の保険料の支払い方法を教えてください
A4:国民健康保険料の支払い方法には、口座振替や振込用紙を用いた金融機関・コンビニ・役所の窓口での支払いなどがあります。ただし、支払い方法については、自治体や健康保険組合ごとに決められているため、居住の自治体のホームページで詳細を確認しましょう。
まとめ
フリーランスは国民皆保険制度のもと、公的医療保険への加入が義務付けられています。ケガや病気になった際に、収入に関係なく保険診療を受けられることが、その大きな理由の一つです。フリーランスは適切な経費を計上して所得を調整することで、保険料を軽減することが可能です。
フリーランスが加入できる公的医療保険には、市区町村の国民健康保険、社会保険の任意継続、家族の社会保険、各種の国民健康保険組合などが挙げられます。
自治体の国民健康保険へ加入する場合、役所(役場)の窓口で手続きすることが可能です。オンラインや郵送などへの対応については自治体によって異なるため、利用条件とあわせて各自治体の公式ホームページで確認しましょう。
※数値に関する情報は、2025年3月27日時点の情報を反映しています。